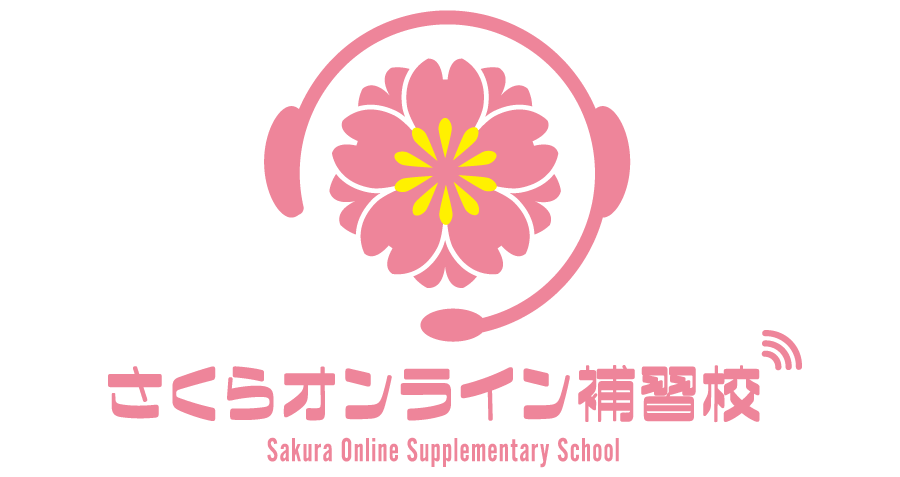節分(せつぶん)は、日本の伝統行事で毎年2月3日ごろに行われます。「季節の分かれ目」とされ、厄除けや無病息災を願う風習があります。
「節分」とは「季節を分ける日」という意味を持ち、昔の暦では立春・立夏・立秋・立冬の前日を指しました。特に立春の前日は新年の始まりと考えられ、重要視されました。
この行事の起源は中国の陰陽道に由来し、昔の日本では季節の変わり目に邪気(鬼)が入りやすいとされていました。そこで、鬼を追い払い、福を呼ぶための儀式が行われるようになりました。
節分といえば「豆まき」が有名ですよね。平安時代の宮中行事「追儺(ついな)」が起源とされ、鬼を追い払うことで災厄を除く目的がありました。豆には「魔を滅する(まめ)」の意味があり、炒った豆をまくことで鬼を払い、福を招くとされています。
節分は、邪気を払い福を招く日本の伝統行事です。豆まきを楽しみながら、家族で日本の文化に触れてみてはいかがでしょうか。