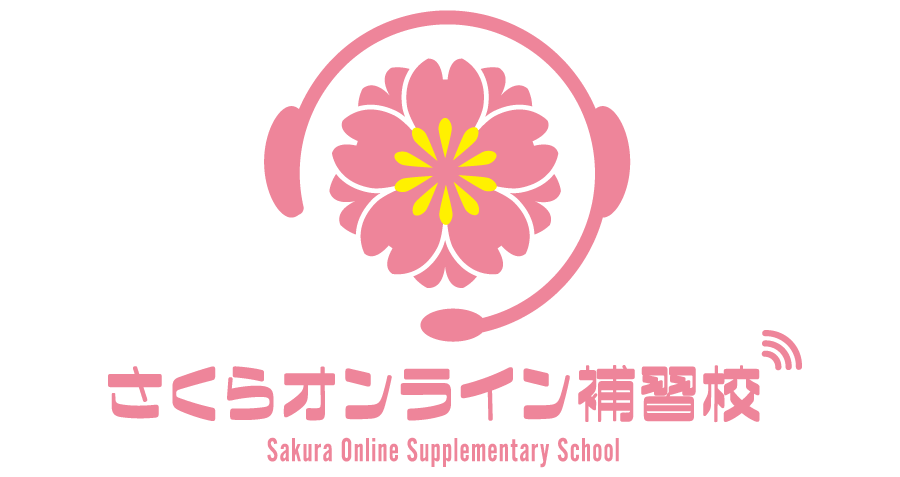恵方巻(えほうまき)は、節分の日に特定の方角を向いて食べる太巻き寿司のことです。この習慣は、関西地方を中心に広まり、現在では全国的に親しまれています。では、恵方巻の由来とは何なのでしょうか?
恵方巻の起源には諸説ありますが、江戸時代から明治時代にかけて大阪の商人たちが商売繁盛を願いながら巻き寿司を食べたのが始まりとされています。また、一説には花街の遊びとして広まったとも言われています。いずれにせよ、福を呼び込む食習慣として根付いていきました。
恵方巻は、その年の縁起の良い方角(恵方)を向いて無言で食べると願いが叶うとされています。これは、福を逃さず取り込むために途中で話をしないという意味があります。
また、具材には「七福神」にちなみ7種類の具材を使うことが多く、縁起の良い食べ物として楽しまれています。
今年の節分には、恵方巻を味わいながら、福を呼び込んでみてはいかがでしょうか?