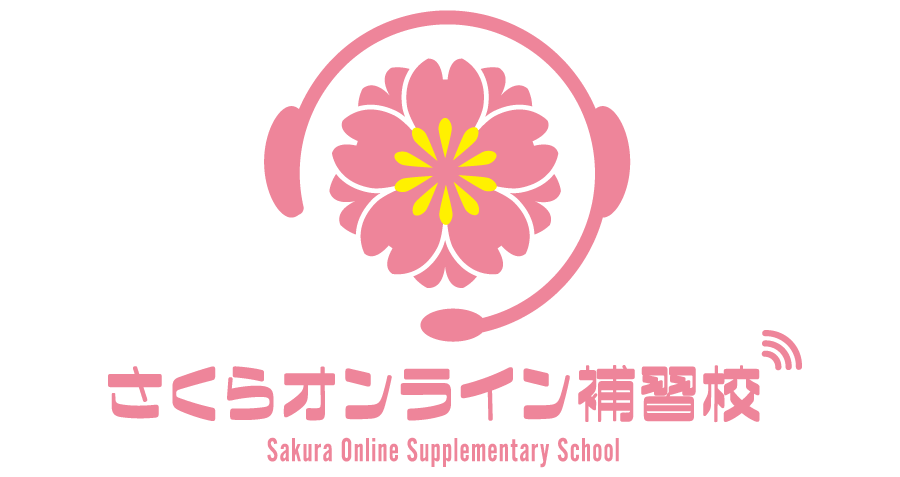毎年2月11日は「建国記念の日」として祝われていますが、実はこの日が日本の建国日として厳密に定められているわけではありません。では、なぜこの日が建国を記念する日として選ばれたのでしょうか?その背景には、神話や歴史的な経緯が関わっています。
「建国記念の日」のもとになったのは、かつての「紀元節」です。紀元節は、日本書紀に記された神武天皇の即位日とされる紀元前660年2月11日を祝う日でした。神武天皇は日本の初代天皇とされていますが、その存在や即位の日付には歴史的な証拠がなく、神話の要素が強いとされています。それでも、長い間、日本の建国を祝う日として紀元節は受け継がれてきました。
しかし、第二次世界大戦後、GHQの占領政策の影響で紀元節は廃止されました。その後、日本国内では伝統的な祝日を復活させようという声が高まり、1966年に「建国記念の日」として再び制定されました。ただし、「建国記念日」ではなく「建国記念の日」とされたのは、特定の歴史的な出来事を指すのではなく、日本の成り立ちや発展そのものを祝うことを目的としたためです。
世界の多くの国では、独立記念日や革命記念日など、具体的な出来事を祝う日が建国記念日となっています。しかし、日本の場合は、神話を含む歴史の流れを大切にし、国家の成り立ちを広く祝う日として位置づけられています。この独自の形を持つ祝日は、日本の歴史観や文化の特徴をよく表しているとも言えるでしょう。