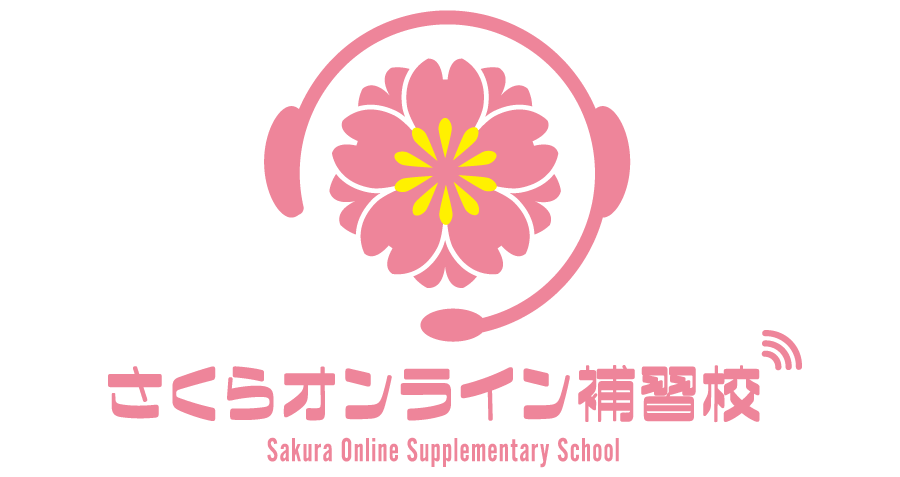1年の中で2月だけが28日(うるう年は29日)と他の月よりも短い理由をご存じでしょうか?これは、古代ローマ時代の暦の仕組みに由来し、日本でも明治時代に現在の形となりました。
古代ローマでは、最初の暦が10か月(304日)しかなく、3月が1年の始まりでした。やがて、ローマ王ヌマ・ポンピリウス(紀元前8世紀)が冬の期間も考慮し、新たに1月と2月を追加しました。しかし、当時の迷信により、偶数の月は不吉と考えられ、1年の総日数を奇数にするため、2月が28日となったのです。
その後、ユリウス暦が導入され、ほとんどの月が30日または31日になりましたが、2月だけは元の形を維持し続けました。さらに、カエサルの後継者アウグストゥスが自分の名を冠した8月(August)を31日にするため、2月の日数はさらに削られることになりました。
日本では、明治6年(1873年)に**グレゴリオ暦(太陽暦)**が正式に採用され、それに伴い2月が28日(うるう年は29日)となりました。
それ以前の日本では**太陰太陽暦(旧暦)**が使用され、1か月は基本的に29日または30日で構成されていました。そのため、旧暦の2月は特に28日と決まっていたわけではなく、年によって変動がありました。
明治政府は西洋化を進めるため、明治5年12月3日を明治6年1月1日とすることで、急速にグレゴリオ暦へ移行しました。この時から、日本の2月も西洋と同じく28日(うるう年は29日)と固定されました。
2月の日数が少ないのは、古代ローマの暦の影響が現代にまで続いているためです。そして、日本でも明治6年にグレゴリオ暦を導入したことで、現在の形が定着しました。日本の暦の変遷を知ると、日常のカレンダーの見え方も少し変わるかもしれませんね。